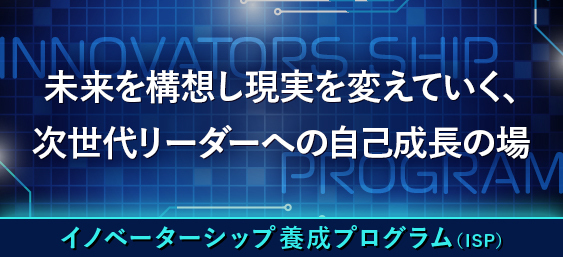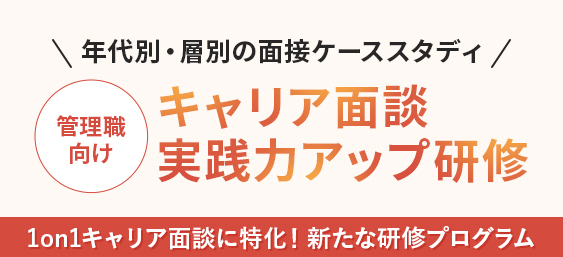スマホは教えてくれない– 【書評】アンデシュ・ハンセン著、久山葉子訳『スマホ脳』(新潮新書)

スウェーデンの精神科医である著者は、本書を著す1年前、
自分がスマホに1日3時間近く費やしていると気づき、ショックを受けた。
何をしていても手がスマホに伸びる。
読書が好きだったはずなのに、本に集中するのが難しくなった。
しかも、メンタルの不調を訴えて受診する人の数が激増している。
デジタル化したライフスタイルは何をもたらしたのか。
著者は多くの先行研究を参照しながら、「スマホ脳」の危険性を解き明かしていく。
大前提として、著者が強調するのは、「人間の脳はデジタル社会に適応していない」という事実だ。
人類は地球上に現れてから大半の時間を、狩猟と採集によって暮らしてきた。
著者曰く、私たちの脳は今もサバンナで暮らしている。
カギになるのは脳内の報酬物質とも呼ばれるドーパミンの働きだという。
ドーパミンの量は、食べ物や他者との交流などによって増えるが、新しい情報によっても増える。
いずれもサバンナで生き延びるために発達した仕組みだが、
現代社会において、新しい情報への欲求は、スマホ依存に繫がってしまう。
スマホやSNSの開発者らは、こうした人間の脳の仕組みを詳しく研究し、利用しているという。
そして、「脳のハッキングに成功した」。
彼らの目的は、私たちから少しでも多くの時間を奪うこと。
私たちの“注目”をめぐる「軍拡競争」はいっそう激しさを増している。
スマホ依存によって、現代の貴重品になってしまったものがある。
「集中力」と「記憶力」である。
大学生500人を対象に集中力と記憶力を調べるテストをしたところ、
スマホを教室の外に置いた学生の方が、
サイレントモードにしてポケットにしまっておいた学生より良い結果が出た。
ポケットに入っているだけで、スマホを無視することに処理能力を使ってしまう結果だろうと、著者は言う。
商談の時も気をつけた方がいい。
テーブルの上にスマホを置いた群と、置いていない群で、知らない人と話してもらう実験では、
視界にスマホが入っていた人たちの方が「あまり楽しくない」「共感しづらい」と感じていた。
これもまた、スマホに気を引かれ、目の前の相手に集中できなかった結果だとみられる。
集中力や記憶力が衰えたとしても、覚えられる数字の桁数が少なくなる程度なら、
それほど問題ないと感じるかもしれない。
今や、あらゆる情報はインターネットの中にあり、覚えていなくても検索すれば事足りる。
しかし、記憶は個人的な体験と融合され、「知識」として構築されるという。
知識とはもちろん、情報の羅列ではない。
私たちは脳内に根づいた知識を用いて、世の中をあらゆる角度から捉え、深く考察している。
スマホ脳によって、そうした思考力が失われているとしたら、取り返しがつかない。
しかも、この社会変革は、まだ始まったばかりに過ぎない。
著者は「スマホというテクノロジーが、人間を2・0バージョンにするよりも、むしろ0・5バージョンにしてしまう」と警告する。
本書が提唱する対抗策はシンプルである。
「睡眠を優先し、身体をよく動かし、社会的な関係を作り、スマホの使用を制限すること」。
とりわけ運動は有効で、1日5分、体を動かすだけでも効果がある。
週に3回、45分程度、息が切れて汗をかくまで運動するとなお良いという。
SNSやメールをチェックする時間を決める。
人と会う時にスマホをマナーモードにして遠ざける。
腕時計や目覚まし時計を使い、スマホを見る時間を減らす。
小さな工夫の積み重ねで、スマホ脳からの脱却を図れるかもしれない。
私たちがライフシフトしていく現代において、最新テクノロジーとの付き合いは欠かせない。
しかし、スマホに毒されたスマホ脳に陥ってしまえば、
集中力、記憶力、ひいては思考力そのものが衰えかねない。
自らのキャリアを振り返り、強みを見つけて、人生100年時代を豊かに生き抜くための海図を描く。
未来を変えるようなイノベーションを起こす。
そんな生き方改革を実現するための答えは、決してスマホの中にはない。
スマホやSNSとうまく付き合いながら、体を動かし、人に会い、本を読み、深く眠る。
現代においてライフシフトをめざす私たちに不可欠なライフハックだと言えるだろう。