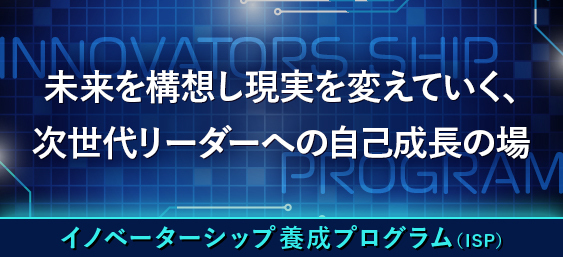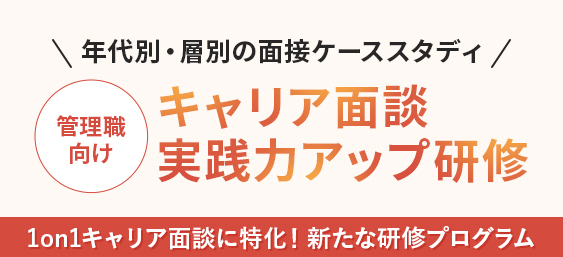脳が求める生き方とは – 【書評】林成之著『脳に悪い7つの習慣』(幻冬舎新書)

書評 林成之著『脳に悪い7つの習慣』(幻冬舎新書)
「なんも言えねえ!」。
2008年の北京五輪で、競泳男子100メートル平泳ぎを2大会連続で制した北島康介選手の言葉を、
ご記憶の方は多いだろう。
予告通りとなる世界新記録での金メダルに、「強かったですね」と声をかけられた北島選手は、しばし絶句し、そう叫んだのだった。
この後、本書の著者である林成之・日本大学名誉教授の『〈勝負脳〉の鍛え方』(講談社現代新書)が売れに売れた。
競泳の日本代表チームが、脳科学を勝負強さにいかそうと、著者を講師として招き、北島選手らが熱心に耳を傾けたと報じられたからだ。
教えの一つが、「ゴールを意識するな」。ゴールは近いと思った瞬間、脳が「もう頑張らなくてもよい」と考えてしまうからだという。
著者によれば、脳の自己報酬神経群と呼ばれる部分が、「ごほうびが得られた」という結果ではなく、
「ごほうびが得られそうだ」という期待によって働くことに起因する。
競泳のゴールは決まっているので、ゴールを意識しないことは難しい。
そこで著者は、最後の10メートルを“マイゾーン”と捉え、「ここからが勝負だ」という意識を持つよう指導したという。
かように「勝負脳」で有名な著者だが、本書は少し趣が違う。
北京五輪の後、著者のもとにはスポーツ界やビジネス界から、「勝負脳」について話してほしいという依頼が殺到した。
その求めに応じながら、著者のなかで「『勝負』という言葉が、少し誤解を招くものであったのではないか」という思いが募っていった。
なぜなら「本来、脳が求めている生き方に、『勝負』というものがなじまない」からだ、という。
ただ勝つためでない、脳が求める生き方とは。それが本書の主題である。
著者はもともと脳神経外科医で、瀕死の状態にある患者の体を冷やし、脳の温度を下げることで、
脳神経細胞の死滅を防ぐ「脳低体温療法」の開発者として知られている。
本書では、日本大学医学部付属板橋病院の救命救急センター立ち上げに携わり、新療法を確立するまでの経験も語られる。
この経験談に、著者の説く脳のしくみのエッセンスが集約されていると言っていい。
瞳孔が開き、呼吸が停止した患者さんであっても、ケタ違いの医療をほどこし、社会復帰させる――。
著者はセンター開設に当たり、当時では無謀とも思われた高い目標を掲げた。
そして目標達成のため、医療設備の充実を図るのみならず、すべてのスタッフに三つの約束を課した。
「否定的な言葉を使わない」「明るく前向きでいる」「仲間の悪口を言わない」。
言葉にすると簡単なようだが、過酷な救命救急医療の現場で、この3箇条を守るのは容易ではない。
思わず3箇条に触れるような言葉が口をついて出ると、スタッフたちは互いに「いま、疲れたって言ったよ」などと指摘し合って、
意識を変えていったという。
ついに著者らは新療法を確立し、瞳孔が開いた状態で運ばれてきた患者の実に4割を社会復帰に導く。
“奇跡”とも称されたその成果は、脳死と判定された息子をなすすべなく見送った柳田邦夫の『脳治療革命の朝』(文藝春秋)に詳しい。
「私たちの目標は、医学の世界にいれば、誰もが『無理だ』というレベルのものであったと思います。
……これは、私が脳のしくみにもとづき、自分とチームを高めようと常に心がけていたことがもたらした結果であると思っています」。
著者は本書で、このように総括している。
著者が自ら活用した脳のしくみとはなにか。
本書によれば、目から入った情報は大脳皮質神経細胞によって認識され、「A10神経群」と呼ばれる部分に到達する。
このA10神経群は、危機感をつかさどる扁桃核、好き嫌いをつかさどる側坐核、
意欲や自律神経をつかさどる視床下部などが集まってできており、ここで「感情」が生まれる。
A10神経群は、送られてきた情報に対し、〈好き〉〈嫌い〉といったレッテルを貼る。
脳内ではその後に、「理解」「思考」「記憶」といった過程が控えている。
このため、ある情報にいったんマイナスのレッテルを貼ってしまうと、脳の機能がしっかり働かなくなるのだという。
第1箇条の「否定的な言葉を使わない」を実践することで、スタッフたちの脳の機能が高まり、
チーム全体のパフォーマンスも上がるというわけだ。
第2箇条の「明るく前向きでいる」も、第1箇条と似ている。
本書によれば、人間の脳には「生きたい」「知りたい」「仲間になりたい」という三つの本能がある。
なかでも脳の原点とも言うべき「知りたい」を発達させるうえで大切なのが〈興味〉だ。物事への興味を失い、
「何をやっても面白くない」などと感じていると、脳の神経伝達路の機能は衰えてしまう。
何事にも興味を持ち、日々を明るく前向きに過ごす姿勢が、脳を活性化させ、深い思考や独創的な発想を生むのだという。
第3箇条の「仲間の悪口を言わない」は、脳のクセと密接に関わっている。
著者によれば、脳には自分を守ろうとする「自己保存」と、
統一性や一貫性が保てなくなる情報を避けようとする「統一・一貫性」という二つのクセがある。
これらにはプラスの作用もあるが、人が間違いをおかす原因にもなる。
例えば、私たちはしばしば、自分と反対の意見を言う人のことを嫌いになってしまう。
意見が違っても嫌いになる必要はなさそうだが、脳が自らの意見と異なるものを「統一・一貫性」に外れるために拒否することが影響しているという。
「自己保存」のクセによって、相手を論破しようとすることもある。著者に言わせれば、これらは脳のクセが過剰反応した結果なのだという。
こうした脳の“悪癖”を克服するために、著者は「自分を捨てる」「立場を捨てる」という意識が大切だと指摘する。
「こういう人は苦手だ」といった先入観を取り払い、「良いところを見つけよう」という姿勢で臨んでみる。
異なる意見をシャットアウトせず、まずは耳を傾けてみる。
このように「相手の立場に立ち、違いを認める力」こそが、脳をいかすカギになるという。
脳が求める生き方とはなにか。著者の答えは「違いを認め、共に生きる」こと。
人に興味をもち、好きになり、心を伝え合い、支え合って生きていく。脳が望んでいるのは、そんな生き方だという。
ライフシフトもまた、競泳のように決まったゴールをめざす、一回限りの勝負ではない。
人生の新しい路を切り開き、仲間とともに歩んでいく旅だ。理解力、思考力、記憶力、発想力、無私になって人の話に耳を傾ける力……。
脳の機能を総動員しながら進んでいく長い旅路なのだ。
脳の本能に従って、肯定的な言葉で語り、明るく前向きな姿勢を貫き、人の良い面に目を向ける。
私たちがライフシフトをしていくうえで心に留めるべき指針であろう。