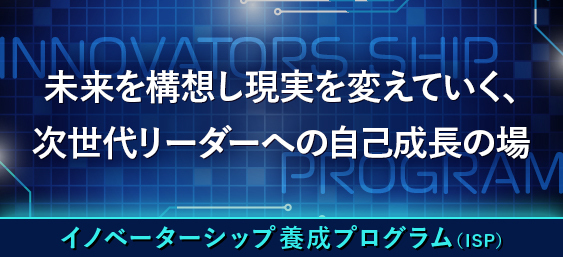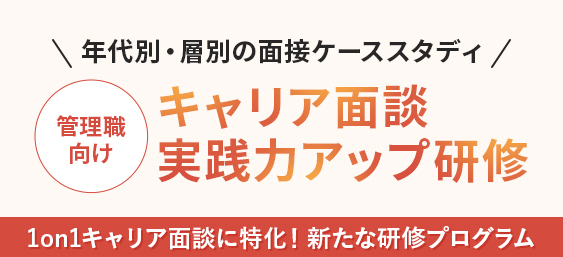「自分探し」をするよりも -【書評】大竹文雄著『競争社会の歩き方 自分の「強み」を見つけるには』(中公新書)-

書評 大竹文雄著『競争社会の歩き方 自分の「強み」を見つけるには』(中公新書)
「競争社会」と聞いて、あなたは何をイメージするだろうか。
弱肉強食、人間性を歪める、格差……。インターネットで検索すると、
そうした表現が並ぶとして、筆者は「日本では否定的な意味でとらえられているようだ」と指摘する。
ところが、そんな言葉が新書のタイトルに冠され、私たちは思わず手を伸ばす。
それは私たちの多くが、心のどこかで、「競争社会を生き抜きたい」「自分の強みを見つけたい」と願ってやまないからだろう。
本書は経済学の視点から、生きるヒントを与えてくれる。
筆者は日本において「証拠に基づく政策立案」(Evidence-Based Policy Making : EBPM)を牽引する気鋭の経済学者である。
行動経済学をはじめとする経済学の研究成果を、平易な言葉で語り、社会に還元してきた。
最近では新型コロナ対策をめぐり、政府の分科会メンバーに選ばれ、noteを通して自らの主張を伝え続ける。
まん延防止等重点措置の延長に、早くから疑問を呈し、反対していたことは記憶に新しい。
一連の発信は今月、政策起業家プラットフォームPEP(Policy Entrepreneur’s Platform)が主宰する
第2回PEPジャーナリズム大賞のオピニオン部門賞を受賞。
「専門家の立場から冷静に状況を解説し、毅然とした態度でEBPMの必要性を説いた」と評された。
本書もまた、経済学の思考法を広く社会に伝えんとする一冊だ。
たとえば、家電量販店がよく掲げる「他店より価格が高ければ対抗します」という広告。
私たちの多くは「この店はできるだけ安い価格で品物を売ってくれる消費者思いの店だ」と感じてしまう。
だが、ある店が同じ地域のライバル店に「1円でも高ければ安くする」という価格競争を仕掛ければ、
際限のない値引き競争で双方の利潤が減り、得をするのは消費者だけということになってしまう。
すなわち、こうした広告の真の狙いは、ライバル店に「価格を下げるなよ」と警告することにあるという。
経済学の世界では、「暗黙の共謀」とすら呼ばれているそうだ。消費者に対する競争の偽装とでも言えようか。
このように筆者は、身の回りのあらゆることを、経済学のフィルターを通して解説してみせる。
経済学に馴染みの薄い私たちは、経済学の扱う分野の幅広さと、それが与えてくれる新しい視点に驚かされる。
競争の本質をつく研究の一つとして筆者は、競争よりも協力を重視する教育は、
教育の意図と真逆の結果をもたらしている可能性がある、
との研究結果を紹介している。
「反競争的な教育を受けた人たちは、利他性が低く、協力に否定的で、……やられたらやり返すという価値観をもつ傾向が高く、
再分配政策にも否定的な可能性が高い」教育における反能力主義、平等主義は結果として、
努力さえすれば誰もが成功できるはずだという努力主義を広め、
「所得が低い人は怠けているからだという発想を植えつけることにつながった可能性がある」というのだ。
皮肉で、衝撃的な分析である。
とはいえ、競争社会では、すべての人が思う通りの結果を得られるわけではない。
では、競争の前向きな価値は一体どこにあるのだろう。
お笑いコンビ「ピース」の又吉直樹さんが2015年、第153回芥川賞を受賞した小説「火花」。
天才肌だが売れない漫才師・神谷が、神谷を師と仰ぐ後輩芸人の徳永にこう説く場面がある。
「漫才はな、一人では出来ひんねん。……もし、世界に漫才師が自分だけやったら、こんなにも頑張ったかなと思う時あんねん」
「周りに凄い奴がいっぱいいたから、そいつ等がやってないこととか、そいつ等の続きとかを俺たちは考えてこれたわけやろ?
ほんなら、もう共同作業みたいなもんやん」
同書には経済学的なメッセージが見事に込められている、と筆者は言う。
お笑いの世界で世に出る人は、ほんの一握りに過ぎない。
今日も多くの挑戦者たちが去って行く。ただし、彼らは確実に何かを手にしている。
競争社会に生きる私たちが、生涯たった一つの競争に賭けるのはまれである。
多くの場合、ある競争を終えると、新しい分野の挑戦へと向かう。
筆者は「競争が繰り返された結果、自分が真に活躍できる場を見つけられる確率が高まる」
「競争の促進は、それぞれの長所を見出し、それを活かす方向へと人々を導く」と強調する。
競争によって、「自分探しをするより」も、「自分の長所を知って創意工夫ができるようになるはずだ」と。
経済学では常識とも言える競争のメリットを、漠然としたイメージだけで否定しないでほしい。
身の回りの出来事に、経済学の思考法を当てはめ、競争を前向きに捉え直してみてほしい。
筆者のメッセージは一貫している。
本書が出版されたのは2017年、筆者が56歳のときだ。
繰り返しになるが、筆者は「競争」というものを人間の強みの形成プロセスという視点から再評価すべきだと主張する。
努力しても物事が常に思うように運ぶわけではない。芸人の世界ほどシビアではないかもしれないが、
企業社会でも成功もあれば失敗もある。
しかし、これからの職業人生を考えるにあたり重要なことは結果ではない。
切磋琢磨してきたこと自体に意味があるのである。
そして長く競争環境に身をおいてきた人ほどその人の中に知らず知らずの間に強みがしっかりつくられているということだ。
同時に筆者は次のようなことも述べている。
年齢とともに人が「イノベーティブ」でなくなるという認識があるとすれば、それは間違いであって、
以前は職業人生の終点年齢が今よりもずっと早かったため、
残り時間との関係でキャリアの終盤でイノベーティブな取り組みをしても収穫の見込みが低く、
そのためあえて新しい取り組みに乗り出すインセンティブに欠けていたにすぎないのだと。
ライフシフトによって新しい取り組みに挑戦する機会は豊かになり、その成果を享受できる時間も伸びる。
我々は長く競争のただなかに身を置いてきた。その年月を通して、
多くのものを得、自らへの理解を深めてきた。だからこそ、何歳になっても強みを見つけることができる。
ラフシフトにあたってどこかに「自分探し」の旅に出かける必要はないのである。
必要なものはすでに自らの中にある。
それをどう整理し直し、引き出し、社会で発揮するかが問われるのである。
筆者のその後の活躍が、なによりも、その証左になっているのではないだろうか。